太宰の「佐渡」について
前稿の佐渡旅行記の冒頭、「私は太宰程の感受性はないにしろ、死にたくはないがその淋しさというものを体験してみようと思う。」と書いた。実は、その太宰の言う淋しさとは何かについて理解が不十分なままであった。旅から帰って、作品を読み返しつつ、考えたのが本稿である。読んでいただける場合は下の「Read the rest of this entry」を押して下さい
太宰治は、短編「佐渡」で佐渡の「寂しさ」について、こう記している。『佐渡は、淋しいところだと聞いている。死ぬほど淋しいところだと聞いている』。その、死ぬほどの淋しさを、夷港(多分現在の両津港だろう)の、一番良いとされている「福田屋」と言う旅館に投宿した夜、感じている。
夜半、ふと目がさめた。ああ、佐渡だ、と思った。波が、どぶん、どぶんと聞える。遠い孤島の宿に、いま寝ているのだという感じがはっきり来た。眼が冴えてしまって、なかなか眠られなかった。謂わば、「死ぬほど淋しいところ」の酷烈な孤独感をやっと捕えた。おいしいものではなかった。やりきれないものであった。けれども、これが欲しくて佐渡までやって来たのではないか。うんと味わえ。
太宰治 「佐渡」より … 以下同様
太宰は、「孤独」というものをこれまで嫌と言うほどに味わっているはずである。このことは、たとえ私のように「佐渡」以外に「津軽」、「走れメロス」、「斜陽」、「右大臣実朝」、「人間失格」(*)……しか読んだことのない人間でも、津軽人特有の内向的な性向を知っている者は、太宰のような感受性の敏感な人間が、仮初にも「死ぬほど」という形容動詞を使うことにただならぬものを感じるのだ。しかし、 私は、この「佐渡」を読む限りにおいて、新潟港を出港して、夷港(現両津港)に到着し、福田屋に投宿して夜半に目覚めた時『死ぬほど淋しいところ』の酷烈な孤独を感じるまでの経過が良く理解できなかったのである。
本編の初めから辿って見よう。汽船に乗って思いの外早く島が見えたのに狼狽する。前日、高等学校での講演が終わった後、新潟の海岸から望見したのは佐渡かと生徒に聞いて、そうだと言う答えを得たのに対して、生徒たちが自分の早合点を嘲笑して否定するのが気の毒になってそうですと答えてその場を取り繕ったのではないかという疑念を持つ。佐渡行きの汽船に乗っていながら、眼前の島は何ですかと言う質問を発することを逡巡する。そして、軽はずみに佐渡行きを決めてしまった自分を呪詛する。以上が太宰が佐渡に上陸するまでの、心の中の舞台設定と考えよう。この背景の中で、太宰はたまたま居合わせた福田屋の番頭の提灯を見て、これまで持っていた相川行きの計画をほとんど発作的に 変更して、夷に投宿することとする。宿に着いても前日の講演の緊張が解けないのか寛ぐことなく端座している。夕食の後裏町を歩き、料亭に入り、自分のこだわりのために不満を募らせて宿に戻る。ここまでが本人の行動。その夜、 「『死ぬほど淋しいところ』の酷烈な孤独感をやっと捕えた 」のである。その時、さらにこのようにも書いている。
床の中で、眼をはっきり開いて、さまざまの事を考えた。自分の醜さを、捨てずに育てて行くより他は、無いと思った。
「自分の醜さ」とは何だろうか。「佐渡」に書かれている文章から拾うと、自分が昨日一日に自分の中に招来した狼狽、疑念、逡巡、こだわり、呪詛、これらを自分の醜さと言っているのではないか。それらすべてをまた呪詛しつつ、自分の宿命と言うものを背負って生きて行くしかないということの確認であったのだろう。これも一つの「淋しさ」の形であると言うのは牽強付会過ぎだろうか。
夜が明けて、太宰は相川行きのバスに乗る。車中および相川到着後も、太宰はしきりに佐渡には何もないと言う。
道が白っぽく乾いている。そうして、素知らぬ振りして生活を営んでいる。少しも旅行者を迎えてくれない。鞄を抱えて、うろうろしているのが恥ずかしいくらいである。(中略) 何も無いのがわかっている。はじめから、わかっている事ではないか。 (中略) 私は、もうそろそろ佐渡をあきらめた。(中略) まちは自分に見向きもせず、自分だけの生活をさっさとしている。私は、のそのそ歩いている自分を、いよいよ恥ずかしく思った。
ここで初めて、「淋しさ」に関係する文章に出会う。「少しも旅行者を迎えてくれない」「 まちは自分に見向きもせず、自分だけの生活をさっさとしている 」と。乾燥した一言でいうと疎外感である。
太宰は、佐渡到着前に「佐渡には何もない」と言うことを、繰り返し繰り返し述べているが、それは期待の裏返しであって、その期待が裏切られた時に自分が受けるショックを和らげるために、あらかじめ自分の心に予防線を張っておいたのだと思う。上述の引用で「 私は、もうそろそろ佐渡をあきらめた。」と言っているのは、何かを期待していたことの反語である。何を期待していたのかは、漠たるものが一杯ありすぎて言葉では表すことのできないものであったかも知れない。夷の宿で夕食を摂った後裏通りを歩き、料亭を見つけて入る際にこう書いている。
やっと見つけた。軒燈には「よしつね」と書かれてある。義経でも弁慶でもかまわない。私は、ただ佐渡の人情を調べたいのである。
ここでは「人情」に触れることなく、不満を抱えて宿に戻ることになったが、そのような目で見ると、夷だけでなく相川も含めて宿の女中さんとの会話がいくつか挿入されていて、その中には割合ポジティブな書かれ方がしてあるところもある。太宰の言う「淋しさ」の一つは、月並みだが人との触れ合いと言うものであったということが見えてくる。だが、自分は前述のような「醜さ」を持っているがために、それを過剰なまでに意識しているがために、容易に人と波長を合わせられない「淋しさ」、合わせることができたとしても疲労困憊してしまう、いずれにしてもすべての試みが失敗に終わる徒労を繰り返すという宿命を負っているという「淋しさ」でもあろう。そして、旅の途中でも「何もなかった」ということに対して、自分の予想通りであったという安堵感の裏返しのようなものが垣間見られる。
もう一つ、太宰は「破滅型」の作家であると言われている。これは、自分が本当はこうありたいと願っているのに、どうしようもなくその反対の行動をとってしまうという性向がなすものであって、「佐渡」でも旅の始めに次のように書かれている。
いまはまだ、地獄の方角ばかりが、気にかかる。新潟まで行くのならば、佐渡へも立ち寄ろう。立ち寄らなければならぬ。謂わば死に神の手招きに吸い寄せられるように、私は何の理由もなく、佐渡にひかれた。私は、大変おセンチなのかも知れない。死ぬほど淋しいところ。それが、よかった。お恥ずかしい事である。
太宰が津軽の出身であることから、津軽人の性格の特徴と言われる「じょっぱり」が発揮され、それが本人でもどうしようもない行動になって現れ、この結果に対して自分を呪詛し、内攻して行くと言う状況を通奏低音とすると、今回の太宰の旅が見えてくるような気がする。
さて、これを踏まえて、そしたら自分の旅はどうであったかについては、別稿に譲る
2019/03/04
んねぞう
(*) 太宰の作品で、元友人と称する男が自宅に押しかけてきてもてなしを要求し、さんざん飲み食いした挙句酒臭い息を吹きかけながら「いい気になるなよ」と言い置いて出て行った、というような作品を読んだ記憶がある。これが作者の意識構造を端的に表現しているのではないかと思っているが、題名が思い出せない

 ■ nNEZOU Portal
■ nNEZOU Portal ■ んねブラ(nNEBLUR)
■ んねブラ(nNEBLUR) ■ People I met in India
■ People I met in India ■ Murphy's Lawカレンダー
■ Murphy's Lawカレンダー ■ twitter (旧 X)(@nnezou)
■ twitter (旧 X)(@nnezou)
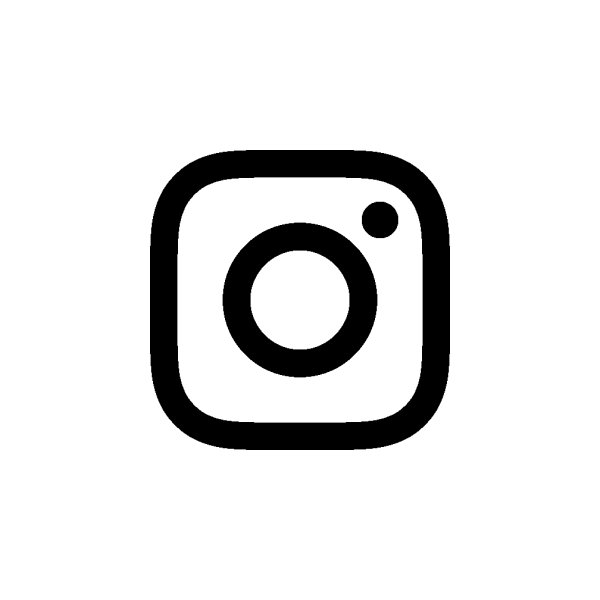 ■ instagram (nnezou)
■ instagram (nnezou)
