「破滅型」の作家 葛西善蔵
2月に津軽に旅行を計画しており、津軽に関する資料や小説などを読んでいる。太宰の「津軽」をおおよそ読み返し、昨年2月に佐渡に行った際に司馬遼太郎の「街道をゆく」を読んだのを思い出し、同じシリーズの津軽に関する本をKindleで購入して読んだ。その中で太宰の「津軽」の引用が随所に見られ、これを引き当てた形での記述がある。また、その中で弘前生まれの葛西善蔵という作家が存在することを知った。一昨日から風邪を引き、今日の土曜日は一日外出せず家に垂れこめていたので、この作家の「哀しき父」、「おせい」、「子をつれて」、「蠢く者」を青空文庫で読んでみた。
破滅っぷりがひどい。葛西の小説を読んだ後だから言えることだが、太宰の破滅ぶりは、天邪鬼が、人の行く方向とは逆に、あたかも夏の小虫が祭りの松明に誘われてふらふらと近づいて行くような、「おいおい、そっちじゃないよ」とでも言いたくなるような風情が、まだある。葛西の場合は、例えば「子をつれて」の場合は、妻が金策に郷里に行っているが、刻々と家の立ち退き期限が近付いているのにもかかわらず、知り合いのKのところに金の無心に通うだけで、いよいよ当日になっても立ち退き先が決まらず深夜に子連れで電車に乗っているところで話が終わる。一体どうすんのよ、と言いたくなる。
持っているものを売ってしまい、売るものもなくなって友人から借金も借り散らした挙句いよいよ窮して最後の頼りに金の無心にKを訪れた「彼」に、Kはこう語る。
「……そりやね、今日の處は一圓差上げることは差上げますがね。併しこの一圓金あつた處で、明日一日凌げば無くなる。……後をどうするかね? 僕だつて金持といふ譯ではないんだからね、さうは續かないしね。一體君はどうご自分の生活といふものを考へて居るのか、僕にはさつぱり見當が附かない」
葛西善蔵「子をつれて」 青空文庫 図書カードNo.51221
「僕にも解らない……」
(略)
「フン、どうして君はさうかな。些ちつとも漠然とした恐怖なんかぢやないんだよ。明瞭な恐怖なんぢやないか。恐ろしい事實なんだよ。最も明瞭にして恐ろしい事實なんだよ。それが君に解らないといふのは僕にはどうも不思議でならん」
(略)
彼にはまだ本當に、Kのいふその恐ろしいものゝ本體といふものが解らないのだ。がその本體の前にぢり/\引摺り込まれて行く、泥沼に脚を取られたやうに刻々と陷沒しつゝある――そのことだけは解つてゐる。けれどもすつかり陷沒し切るまでには、案外時がかゝるものかも知れないし、またその間にどんな思ひがけない救ひの手が出て來るかも知れないのだし、また福運といふ程ではなくも、どうかして自分等家族五人が饑ゑずに活きて行けるやうな新しい道が見出せないとも限らないではないか?――無氣力な彼の考へ方としては、結局またこんな處へ落ちて來るといふことは寧ろ自然なことであらねばならなかつた。
彼の著作はすべてが本人の実人生だという。「表現」の渇望をドライビングフォースとして、 経済的な準備もなく妻子を伴い東京に出たものの、健康にも恵まれず、赤貧洗うがごとき生活で知り合いから寸借生活を続けて、このままではいけないとは思いつつ、なぜいけないのか、その恐ろしさは朧気ながらわかってはいるが行き着くところまで行ってみることを、積極的には肯定しないにしろ、それがむしろ自然なことであるというのだ。
俗世間的に言えば、Kの言い分が正しい。また、父親の香典返しのお茶の鑵を彼に発送するにあたり、憎しみを込めて凹ませて送ったYのような人間も、世間が味方するだろう。
私は勤め人生活が長く、人のことを斟酌するのに幅が狭いので、「言っていることはわかるけど(実のところわかっちゃいない)、まあ、あの人はああだから…」と、できるだけ関係を持たないようにするだろうと思う。 私には、この上記二者の間をどのように考えればよいのか、「彼」の考え方をどう飲み下せばよいのか、考えが纏まらない。
上述の司馬遼太郎の「街道をゆく」では、葛西についてこのように書き記している。
本来、 小説的情景は作家が想像のなかでつくりだすものだが、かれは実際に生きてみて、ナマ身で情景をつくりだした。人生の破綻こそ〝 芸術〟への出発だ、とこの人はいう。
司馬遼太郎. 街道をゆく 41 北のまほろば . Kindle 版. 以下同様
さらに、太宰が弘前高校に入学した早々に書いた英文の作文で、太宰は
〝葛西善蔵はいまの日本でいちばん不幸な作家である〟
とし、
「ほんたうの幸福とは、外から得られぬものであ つて、おのれが英雄になるか、受難者になるか、その心構へこそほんたうの幸福に接近する鍵である」
と書いているそうだ。さらに、司馬は、石坂洋次郎と葛西の交友にも触れた後、こうも書いている。
津軽人石坂あるいは太宰にとって、葛西善蔵は、芸術上の聖者か殉教者のような存在だったのである。
ここまで書かれると、多少なりとも津軽を理解したいと思っている私としては「まあ、あの人はああだから」と乙に澄ましてもいられず、少しは真面目に向き合わなければならなくなる。何だか重い宿題をもらった気分だ。
P.S.
今、一つ思ったことがあるので、断片的ではあるが書き出しておきたい。葛西と太宰の 破滅傾向のパースペクティブについてである。太宰は作家としての活動を始める前に、既に葛西の作品に触れていた。そののち著作活動を進めるにあたって、「東京八景」では自分の生活、社会的な立場がじりじりと破綻に近づいてゆく状況を、克明に、しかもその刹那刹那の状況に、腸(はらわた)がこわばってゆくような感覚と同時に、その破綻への近づき方の微分係数が微小な(微小かどうかは実際わからないが、一種の麻痺状態として)故の、そして自分の見込み通り傾向が悪くなっていることを確認できていることに対する、逆説的な安堵感をもって描写されている。この様子と葛西の作品を比べてみて、太宰が、津軽人特有の含羞を持っている人間として捉えると、自分は裕福な、地方の有力者の家庭で、経済的には何不自由なく育ち、東京の大学にも通った身である。それに引き換え、葛西は自分の芸術に対する理念に徹底的に忠実であるということを明確に意識しており、太宰は始終このことに負い目を持っていたのではないか。自分は不徹底な人間である、その不徹底な人間がこんな小説を書いて、頭の中の別の自分が「へえ、芸術家ってのは、例えば葛西善蔵みたいなものを言うんだと思っていたけど、ほう、あんたも芸術家なの。へえ、そうなんだ」と何かあるごとに頭を擡げて来る、そういうような意識を常に持ち続け、それが彼の生涯を通じた創作の底流にあるような気がする
2020/01/11
んねぞう

 ■ nNEZOU Portal
■ nNEZOU Portal ■ んねブラ(nNEBLUR)
■ んねブラ(nNEBLUR) ■ People I met in India
■ People I met in India ■ Murphy's Lawカレンダー
■ Murphy's Lawカレンダー ■ twitter (旧 X)(@nnezou)
■ twitter (旧 X)(@nnezou)
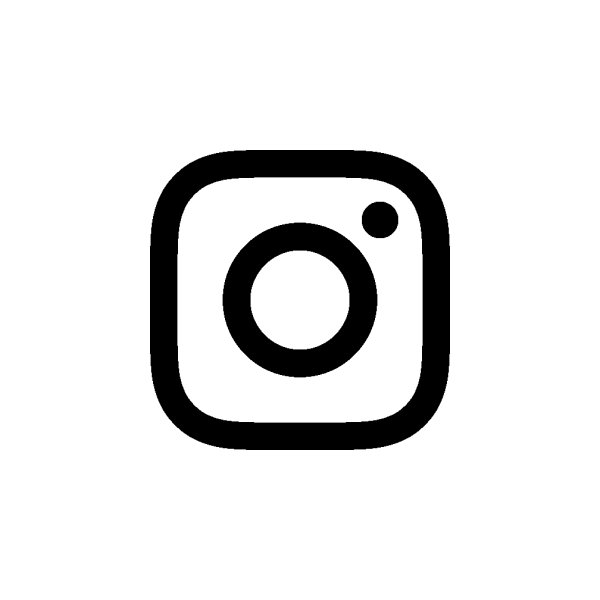 ■ instagram (nnezou)
■ instagram (nnezou)
