津軽三味線の精神性…バッハとの比較
私の車のカーナビにはSDカードに格納したmp3ファイルを再生する機能が付いている。昨日、車を運転していて、ちょっくらCorelliでも聴いてみんべか、と何気なくプレーヤーのスイッチを入れたら、案に相違して突然津軽民謡の、女性の朗々たる歌声が流れて狼狽えた。そのSDカードにはバロック音楽以外にも私のお気に入りの音楽が入っているので、同様にお気に入りの津軽三味線に関連した曲が入っているのは何もおかしくはなく、多分前回再生した時にこの場所で再生を切ったために、今回ここから再生が始まっただけの話である
耳と心がバロック音楽を聴くようになっていたところに突然津軽三味線が飛び込んで来たので、錆び付いた脳内スイッチのレバーをぎしぎしと切り替えているうちに、その両極(バロック音楽と津軽三味線)の違いが朧気ながら浮かび上がって来て、次のような事を思った

津軽三味線は、民謡の伴奏だった三味線を、津軽三味線の創始者とされる神原の仁太坊やその後継者達が独奏楽器として確立させたものだ。当時の主要な聴衆は農民で、三味線には民謡の伴奏としてしか期待されていなかったので、独奏楽器として出現した三味線に対して「三味線、降りでまれ!」(引っ込め)、「カラスだな」(民謡歌手と比べて抑揚のない演奏だなと言う意味か)と散々な言われようだった。これに対して、演者達は、何とかして聴衆の度肝を抜いて耳を傾けさせようと切磋琢磨して成立したのが津軽三味線だ。勝負は音量とテクニックで、「この野郎」、「なにくそ」と言う津軽人一流の頑固、意地っ張り、派手好き、進取の気性が作用して現在の叩きつけるような奏法の津軽三味線が成立した
以上が私の津軽三味線成立に関する大雑把な理解だ。話が飛躍するようだが、タイトルに書いた精神性の話になると、バッハを始めとするバロック音楽の宗教曲に見られる精神性の観点において、私は津軽三味線にその必要性を認めない。なぜならば、津軽三味線は虐げられた階層の人間が、自分の生存をかけた精一杯の叫びであり、聴衆に対する「なにくそ!」、「この野郎!」、「これでどうだ!」と言う挑戦であるからだ。まさに今日一日の露命を繋ぐに足る食べ物を得られるかどうかと言うレベルからくる叫びなのだ。語弊を恐れずに言えば、人間の原罪とか哲学的、宗教的な乙に澄ました議論とは無縁であり、聴いている側としても津軽三味線はとにかく相手の度肝を抜く音量、激しさ、テクニックが全てで良いと思っている
ただし、その演奏の陰に、私は津軽の自然風景、人々の暮らしと言うものを見てしまう。地吹雪の吹きすさぶ冬、一気に花咲く春、稲が青々と育ち、風が田畑を吹き渡る夏、実りの秋を迎え、岩木山を中心とした神域で開催される祭り、そしてそういう中で息づく人々の暮らし。私は津軽生まれでもなく、育った訳でもないのだが、東北南部の生まれで、津軽人と多少職場で付き合ったことがあり、またふとしたことで津軽三味線に触れることがあり、これが縁で何度か冬の津軽を訪れたり、本を読んだりして、徐々に私の津軽三味線観が形成されてきた。それではお前の見る「津軽の風景」とは何かと聞かれれば、写真家 小島 一郎(1924-1964)の写真集「小島一郎写真集成」を挙げたい。そこには、四季折々の津軽の風景、人々の生活が、自身も生まれ育った土地としての主体性をもって描写されている。演奏の影に私が勝手にその風景を思い浮かべているのだろうと言われればそれまでだが、その演者が生まれ育ってきた「津軽」と言うものが背景にあったからこそ演奏、曲そのものが成立し、その裏には共通する郷土愛、もっと言えば原風景の共有があることは誰にも否定できないと信じる。その基盤の上で津軽三味線弾きは津軽人の魂に訴えて来た。私はその原風景を上述の小島の写真に見ている。また、私自身もその欠片を求めて数回カメラを抱えて津軽を旅した。このことは文芸同人誌「澪」でも数回フォトエッセーとして発表もしているし、私の写真blog(んねブラ)にも掲載している
このブログのどこかで書いたと思うが、現在の津軽三味線はその存在の基盤が揺らぎつつある。「揺らぐ」と言う言い方が良くなければ、変わって来ていると言っても良い。今、津軽三味線を弾く人、習っている人は上に書いたような乞食同然の暮らしはしておらず、生活の基盤がしっかりしているからこういうことができるのであって、間違っても神原の仁太坊のように天然痘で視力を失い、三味線しか糊口を凌ぐ術がなく、あまつさえ渡し船の船頭の息子と言う、社会から蔑まれる境涯である訳がない。そのような点から、現代人の奏でる津軽三味線と、当時の三味線弾き達のなりふり構わず「叩く」三味線とは一線を画するものだと思う。本来の津軽三味線は、上述したように、物理的に食べ物(露骨に言えば米の一合、二合)を得るための「叩き」三味線だった。それが現代に生きる日本人の琴線に触れ、全国的に、時には海外公演で熱狂をもって迎えられるに至った。それは喜ばしいことである反面、その時から津軽三味線は「津軽」と言うルーツから乖離を始めた。津軽に生まれず、生活してその自然や人々の生活に触れたことのない演者が増え始めた。もちろん、津軽三味線に魅せられた人達が演奏しているのだから、その精神は受け継がれているのだろうが、その根底で確実に変化が起きていると思わざるを得ないのだ
これが良い、悪いというのではない。私の好きなバロック音楽の勃興期には、それまでのルネッサンス音楽の愛好家たちからはそれこそ「バロック」の本来の意味である「歪んだ」という形容詞が付与されているから、バロック音楽は当時「外道」と思われていたに違いない。しかし今日、バロック音楽は歴とした古典音楽としての一ジャンルとなっていて広く受け入れられていることは誰にも否定できないだろう。このような歴史的視点から、これからの津軽三味線は、地縁を離れて飛躍するという未来もあると思う。固陋な私は、本来の津軽三味線の由来に立脚して、少し距離を置いて見て行きたい、そう言うことである
今後の津軽三味線の発展の過程の中で、或いは奴隷として北米大陸に連れて来られた黒人の間から発祥したジャズのように広まって行き、普遍的なメッセージ性、精神性を獲得するということも考えられるだろう

津軽三味線発祥の地の記念碑
2025/01/03
んねぞう
それにしても、タイトルで津軽三味線の精神性とバッハとの比較とは大きく出たものだな

 ■ nNEZOU Portal
■ nNEZOU Portal ■ んねブラ(nNEBLUR)
■ んねブラ(nNEBLUR) ■ People I met in India
■ People I met in India ■ Murphy's Lawカレンダー
■ Murphy's Lawカレンダー ■ twitter (旧 X)(@nnezou)
■ twitter (旧 X)(@nnezou)
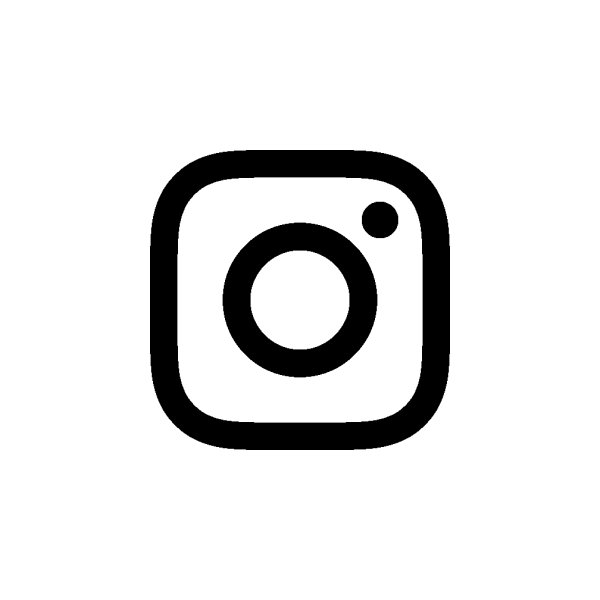 ■ instagram (nnezou)
■ instagram (nnezou)
